



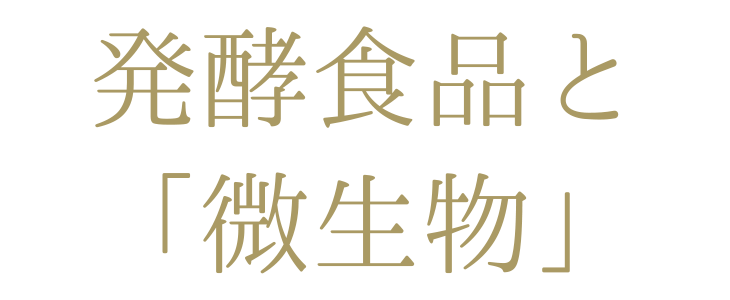 私たちのカラダの中で生み出される酵素の
私たちのカラダの中で生み出される酵素の
年齢とともに減っていき
そのため、不足する酵素を補うた
食物によってカラダの外から酵素を摂り入れる必要があり
生の野菜やフルーツ、発酵食品などに含まれる酵素
中でも注目したいのが発酵食品に含まれる「微生物」の存在
微生物と聞くと、聞きなれない言葉のように思い
ヨーグルトの乳酸菌、味噌や醤油の麹(こうじ)菌、お酒やパンの酵母菌と
みなさんにとっても馴染み深いものになるで
発酵食品に含まれるこれらの菌は
「微生物」と呼ばれる肉眼で見ることのできない小さな
この微生物のもつ「酵素」によって発酵がおこなわれてい
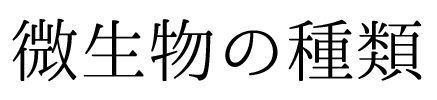
微生物とは、肉眼で見ることのできない、
または細かなところまで観察できず
顕微鏡などで見ることができる大きさの生物の総称です。
微生物は大きく分けて、
「細菌」・「カビ」・「酵母」の3つのグループに分けられます。


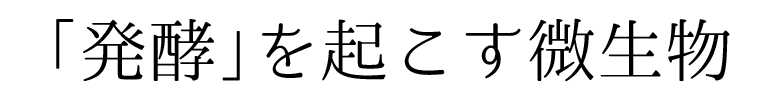
納豆や味噌、日本酒やパンなど、発酵食品はその名の通り
「発酵」によって作られる食品です。
そして、その発酵という化学変化を起こしているものの正体、
それがまさに「微生物」なのです。


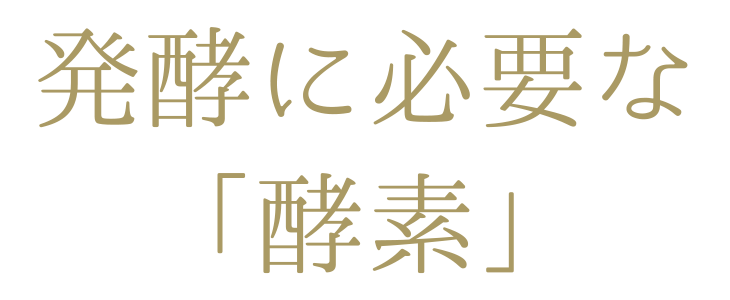 発酵という化学反応を起こす
発酵という化学反応を起こす
微生物のもつ「酵素」
発酵食品は、さまざまな微生物の持つ「酵素」
もともとの食品の成分が「分解」・「合成」
まったく新しい食品へと生まれ変わることでできた食品
微生物が起こす化学変化の中で、
人間の生活に有益な反応のことを「発酵」と呼び
一方で、食品が微生物によって食べられなくなる場合が
その場合は「腐敗」と呼びわけてい

「発酵」には、驚くほどの力があり
すると、もとの食材にはなかった美味しさや栄養価が加わり、新しく魅力的な食品として生まれ変わり
牛乳を発酵させたチーズ、大豆を発酵させた納豆など、発酵後には発酵前にはなかった風味を味わうことができ
また、栄養分析をすると、発酵前にはなかった栄養成分を数多く含んでいることがわかり

微生物の酵素の力によって食材のデンプンや糖、タンパク質が分解発酵されることによって、独特な香りやうま味成分(アミノ酸や核酸など)がつくりだされ
微生物の酵素による分解発酵によってさまざまな種類の栄養成分が生み出され
微生物が他の菌の繁殖を抑え自分の生存を優位にする拮抗作用によって、腐敗菌など人間に害を与える菌を抑えて食品の保存性をよくする力があり
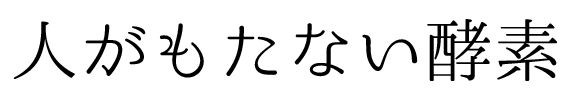
自然界の微生物は、
人間がもっていないような酵素をもって
人間の体内ではつくれない化学物質を
人間には分解できないものも分解してい
食物から酵素を摂ることは、
私たちの体内で不足する酵素の量を増加させるためで
また、私たちの体内では得られない別の生物のもつ
与えてもらうということでもあり
発酵食品を通して微生物のもつ多種多様な酵素を摂る
健康のためにも大切なことなの